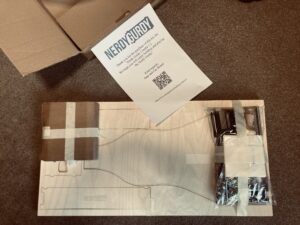Gurdyworld: Bags & Cases
こちらケースの一覧にて、ユーフォニウムやアルトホルンのケースが使えるかもしれんよ、とのこと。金管楽器は扱ったことがないのですが、調べた感じ若干平たいというか内部寸法の高さ幅が十分でも厚みが足りないケースが多そうなイメージ。
私の Helmut Seibert は 58 x 25 x 23 [cm^3] 程度なので、Tom & Will のバリトンケースが丁度くらいかと思って試してみました。

ぎりぎりな収まりっぷりです。円筒形ベースなのでベル径は箱型での奥行きを担保しないです。入ったからよかったのですが、もうちょっと余裕のあるサイズをお勧めします。